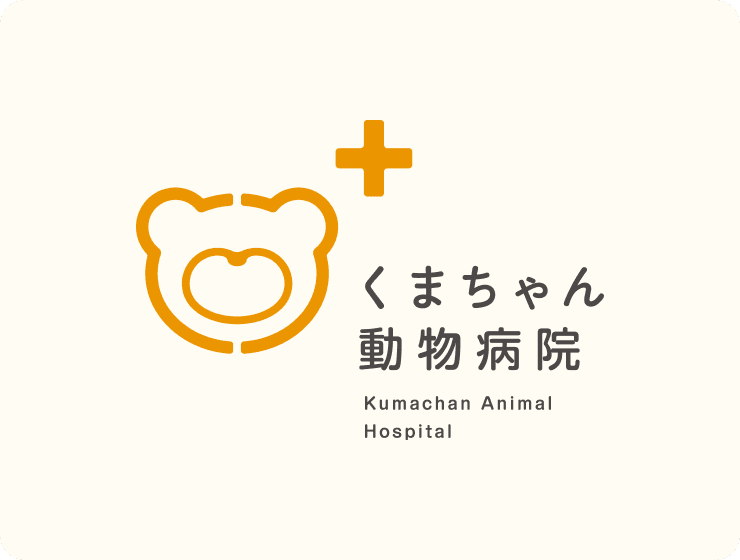犬や猫にとって「心疾患」とはどのような病気なのか、どんな症状が出るのか、そして何より、今まで通りの生活ができるのかと不安を抱かれる飼い主様は多いかもしれません。
しかし、心臓に持病があっても、適切な治療と日々の管理によって、穏やかで快適な毎日を過ごすことは十分に可能です。
今回は、心疾患を抱える犬や猫と暮らすうえでの、日常生活での工夫やご家庭でできる観察のポイントについてご紹介します。

■目次
1.心疾患とは?
2.日常で気づきたい変化と観察ポイント
3.心疾患のある犬や猫のための生活環境づくり
4.緊急時の対応
5.まとめ
【心疾患とは?】
心疾患とは、心臓の構造や機能に異常が起こることで、全身への血液循環に影響が出る病気の総称です。
心臓は血液を全身に送り出すポンプの役割を担っており、その働きがうまくいかなくなると、さまざまな体調の変化や症状が現れるようになります。
犬や猫に見られる主な心疾患は、大きく分けて以下のようなタイプがあります。
<犬に多い心疾患の一例>
◆僧帽弁閉鎖不全症(MR)
小型犬のシニア期に多く、心臓の左側にある「僧帽弁」がしっかり閉じなくなることで、血液が逆流してしまう病気です。
◆拡張型心筋症(DCM)
大型犬に多く、心臓の筋肉が薄くなることでポンプの収縮力が低下し、血液を十分に送り出せなくなります。
<猫に多い心疾患の一例>
◆肥大型心筋症(HCM)
心筋が厚くなることで心臓の内腔が狭くなり、血液の流れが制限されてしまいます。特にメインクーンやラグドールなどの純血種に多いとされています。
【日常で気づきたい変化と観察ポイント】
心疾患の初期には目立った異常が出にくいため、「なんとなく元気がない」「散歩の途中で座り込む」など、ちょっとした変化に気づくことがとても大切です。
日々の中で、以下のようなポイントを意識してチェックしてみてください。
✅呼吸の様子(安静時の呼吸数をチェック。犬猫ともに20~30回/分が目安)
✅咳をしていないか/回数が増えていないか
✅食欲や元気の変化
✅眠っているときの呼吸が苦しそうでないか
✅散歩を嫌がる、動きが鈍いなどの変化
✅お腹がふくらんできた(※胸水や腹水の可能性)
✅急な体重増加はないか(腹水やむくみによることも)
「年齢のせいかな」と思って見過ごしてしまうこともありますが、少しでも気になる変化があれば、早めに動物病院へご相談いただくことをおすすめします。
<こんなときはすぐに病院へ>
下記のような症状が現れた場合、命に関わる可能性があります。ためらわず、すぐに動物病院へご連絡ください。
・呼吸が速く苦しそう、横になることができない
・舌や歯ぐきが紫色〜青白く変色している(チアノーゼ)
・意識がもうろうとしている、または倒れる
・けいれんや突然の失神
・極端なぐったり感、水も食事もとらず反応が鈍い
【心疾患のある犬や猫のための生活環境づくり】
心臓に不安のある犬や猫が、毎日を少しでも穏やかに過ごすためには、環境や生活の工夫が欠かせません。以下のポイントを意識してみましょう。
◆室温・湿度の管理
気温や湿度の変化は心臓に負担をかけることがあります。一年を通して快適な室内環境を保ちましょう。
・夏:室温23~25℃/湿度50~60%
・冬:室温20~23℃
急激な温度変化は発作や呼吸困難の原因になることもありますので、エアコンや加湿器でゆるやかな調整を心がけてください。
◆静かに過ごせる空間づくり
心疾患のある犬や猫は、ちょっとした刺激にも負担を感じやすくなります。
来客時は静かな部屋で過ごさせる、生活スペースは大きな音や頻繁な出入りのない場所にするなど、できるだけリラックスできる環境を整えてあげましょう。
◆無理のない運動
すべての運動をやめる必要はありません。初期〜中等度の段階であれば、室内の移動やゆっくりした散歩が可能なこともあります。
ただし、重度の場合は激しい動きや興奮を避け、体調に合わせた過ごし方を心がけてください。
◆食事の見直し
塩分(ナトリウム)を控えることで、体に余分な水分がたまりにくくなり、心臓の負担を減らせます。
また、タウリン・L-カルニチン・オメガ3脂肪酸などの栄養素も心臓の健康維持に役立ちます。
フードは、獣医師と相談しながら愛犬・愛猫に合ったものを選ぶようにしましょう。
◆投薬を続けやすくする工夫
心疾患の治療では、毎日の投薬が重要です。お薬は決められた時間に、忘れずに与えることが基本となります。
食事に混ぜたり、おやつに包んだりと、できるだけストレスの少ない方法を見つけてあげましょう。
どうしても薬を嫌がる場合は無理に飲ませず、動物病院にご相談ください。薬の形状を変更することで、飲ませやすくなることもあります。
【緊急時の対応】
心疾患をもつ愛犬・愛猫は、急に体調が悪化することがあります。
もしものときに備えて「どう行動すべきか」をあらかじめ知っておくことが、とても大切です。
<応急処置と搬送のポイント>
万が一のときには、慌てず落ち着いて行動することが大切です。
・無理に立たせたり歩かせたりせず、まずは安静に
・呼吸が苦しそうなときは、風を送る・静かな場所に寝かせる
・移動中は体勢を安定させ、できるだけ動かさないように注意
緊急時に迷わないよう、かかりつけの動物病院の連絡先と、夜間や休日も対応している救急病院の情報を、すぐに確認できる場所に控えておきましょう。
【まとめ】
心疾患のある犬や猫との暮らしには、不安や戸惑いを感じることもあるかもしれません。
しかし、正しい知識と日々の丁寧なケアがあれば、病気と上手に付き合いながら穏やかな毎日を送ることは十分に可能です。
毎日の観察・投薬・生活環境の整備・食事管理など、小さな積み重ねが、愛犬・愛猫の体と心の安定につながります。
また、もしものときの備えをしておくことで、落ち着いて対応することができ、大切な命を守ることにもつながります。
愛犬・愛猫の心臓の健康について気になることがありましたら、どうぞお気軽に当院までご相談ください。
■関連する記事はこちらです
・犬と猫の心臓病に注意|咳や呼吸の変化はサイン?初期症状と健康管理のコツ
・犬や猫の肺高血圧症について|症状・診断・治療法を解説
・犬と猫の肺水腫|咳が止まらない…それは肺水腫のサインかも?
・犬と猫の心筋症|咳や呼吸が苦しそう…心筋症の可能性も?
犬と猫の眼のことなら新潟県新潟市の動物病院 くまちゃん動物病院